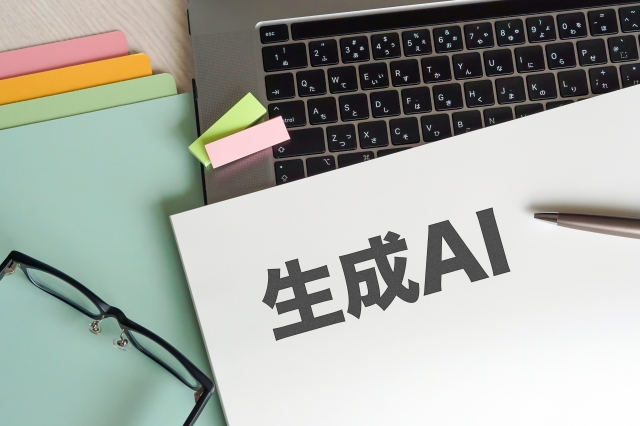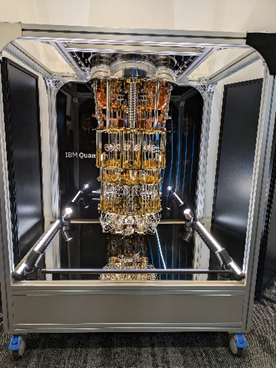トランプ米政権2.0と中小企業の生き残り戦略:多様性を活かす組織づくり
- 2025/2/1
- トピックス

中小企業診断士
ダイバーシティ・シニアコンサルタント
湯浅 尚子
はじめに:トランプ政権2.0がもたらす変化と日本の課題
2025年1月、ドナルド・トランプ氏が「米国第一」を掲げ、アメリカ大統領に返り咲きました。就任直後から環境政策の転換、移民規制の強化、ジェンダー政策の見直しといった数々の大統領令に署名しています。
トランプ政権の復権は我が国の経済にどう波及するのでしょうか、日本の中小企業は経営戦略の見直しを迫られるのでしょうか。本コラムでは、「誰一人取り残さない」を理念とするSDGs〔持続可能な開発目標〕や、世界的な流れであるESG投資〔環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した経営を重視する投資手法〕に注目しながら、特に、多様性の観点で日本の中小企業がどのように対応すべきかを考察します。
1.トランプ政権の政策と多様性への影響
結論から述べると、トランプ政権の政策は短期的には米国内雇用の保護につながるものの、長期的には多様性が生むイノベーションの減退や国際的な競争力の低下を招くと指摘されています。
「ハーバード白熱教室」で知られるマイケル・サンデル教授は、朝日新聞のインタビューi に対し「新自由主義的なグローバル化は、(中略)平均的な労働者には賃金の停滞と雇用の喪失をもたらしました。(中略)所得や富の不平等の拡大に伴い、能力主義的な個人主義が行き過ぎ(中略)、苦しんでいる人に対し(民主党政権からは)グローバル経済の競争に勝ちたければ大学に行け(といわれ)(中略)、労働者は高学歴のエリートに見下されている屈辱感(中略)、社会的名誉や尊敬・承認・尊厳の欠如(中略)、疎外感と、政治に声が届いていないという無力感にさいなまれました。トランプはその憤怒につけ込んだ(中略)」と話しています。
ここから考えると、空洞化した米工業都市の労働者層に尊厳の回復を期待させるようなトランプ氏の政策が魅力的なのには理由があると感じます。しかしその方法は、家父長主義の価値観に基づいた男女の役割分業や排外主義に陥っています。大統領就任演説では「米政府の公式として、きょうから性別は男女の二つのみとする」と宣言し、昨今のDEI〔Diversity, Equity & Inclusion=多様性・公平性・包括性〕の視点に逆行する姿勢を明らかにしました。これは明らかに、時代に逆行し、持続可能性に欠くと感じます。

2.日本における「男女の役割分業」とその課題
「男は男らしく、女は女らしく」「男は社会に出て働き、お金を稼ぎ、女は家事に勤しみ家を守る」そのような価値観は日本にも根強く存在してきました。家父長主義の価値観に基づいた男女の役割分業意識です。しかし、個人の基本的人権を尊重する考え方が進むにつれ、それは本当に理想的な姿なのか、個々人の特性や志向に応じた多様な生き方・家族観が認められるべきではないか、との考え方が注目されるようになりました。
女性でも経済社会でこそ輝ける、仕事の場で活躍できる女性は多く存在します。そのような女性が家事育児に専念しなければならないとしたら、それは社会にとって大きな損失です。男性でも仕事よりも家事や育児が得意な人はいます。そのような男性は、「男は仕事」という固定観念にとらわれず、家庭内でその才能を発揮したほうが良いかもしれません。しかし、男性が育児に積極的に関わるために短時間勤務を希望しても、「出世コースから外れる」という社会的圧力を感じ、選択肢を制限されるケースが少なくありません。
LGBTii の性的マイノリティ当事者は日本では人口の約10%おり、生活する上での多くの困難や精神的な負担を抱え、自殺未遂率は非当事者の約6倍と言われていますiii iv 。
家父長主義の価値観に基づく男女の役割分業といった古い価値観に戻ることは、能力主義で生き残る一握りの勝者以外の人を救うことにはつながらないと考えます。多様な生き方を認めることこそが、自己実現に資するだけでなく、それぞれが自身の持つ特性・才能を活かすことに繋がるからです。

3.多様性とイノベーションの関係:組織の未来を築くカギ
多様性の受容は、単なる倫理的な課題ではなく、企業の競争力強化に直結する経営戦略的要素です。
「世界で最もイノベ―ティブな組織の作り方」の著者・山口周氏は、「これまでに誰も考えたことがない新しい要素の組み合わせがイノベーションの源泉であり、その実現には多様性が不可欠である。」「個人の創造性を組織の創造性に昇華させるには、自由に意見を述べ、アイデア同士が交わる社会的プロセスが必要」と指摘していますv 。つまり、多様な人材が意見を出し合い、互いに影響し合える環境が整ったときこそ、イノベーションが生まれるのです。
ここで重要なのは、単に多様な人材を「受容」するのではなく、「包括(Inclusion)」するということです。つまり、誰もが公平に活躍できる場を提供し、積極的に関与できる仕組みを整えることが、企業の成長に不可欠なのです。

4.ESG投資とSDGs:中小企業が目指すべき持続可能な未来
さらに、近年のESG投資の拡大により、多様性を重視したダイバーシティ経営戦略を推進する企業は投資家からの評価が高まり、資金調達や企業価値の向上につながる傾向にあります。なぜなら、多様性を重視するとリスク管理の強化(法的リスクやレピュテーションリスクの低減)、意思決定の質の向上(ガバナンス強化)、イノベーションの促進と収益性向上(新規市場開拓やビジネス成長)が見込めるからです。 また国連のSDGs(持続可能な開発目標)との親和性があります。「誰一人取り残さない」という理念を掲げ、2030年までに達成すべき17の目標を定めています。特に、「目標5:ジェンダー平等の実現」「目標8:働きがいも経済成長も」は中小企業の組織戦略にとって重要な指針となります。
5.日本の中小企業が取るべきダイバーシティ経営戦略
具体的な取り組みを以下に挙げます。これはほんの一例です。
- 多様な人材の採用・育成
女性・LGBT・高齢者・外国人などの多様な人材の採用、社長の方針発信、受け入れにあたり他の社員向け研修
※属性によって注意すべきポイントは異なります。東京都中小企業診断士協会認定ダイバーシティ研究会vi や一社)日本ダイバーシティ・マネジメント推進機構vii の執筆が参考になります - 柔軟な働き方の推進
レックスタイム制度やテレワーク、ファミリー休暇viii の導入など - 心理的安全性の確保
風通しのよい組織文化を醸成し、意見を言いやすい環境を整備
6.まとめ:持続可能な組織を目指して
経営者と従業員の距離が近く、環境変化に対し迅速かつ柔軟に対応できるのが中小企業の強みです。「省力化・育成・多様性の『3つのチャレンジ』による自己変革に挑むことができれば、企業の規模に関わらず提供する財・サービスの付加価値を高め、持続的な賃上げを実現することは十分に可能であり、それこそが変化の厳しい時代における中小企業のあるべき姿であり存在価値」でもあるでしょうix 。労働人口の減少による深刻な人手不足の中、優秀な人材確保、競争力の強化、イノベーションの促進、国際的な信頼の獲得を実現できます。
トランプ政権の動向に振り回されることなく、中小企業の皆さまには、性別や年齢、国籍、性的指向に関係なく、すべての従業員が働きやすさと働きがいを持って、能力を最大限に発揮できる組織づくりを目指していただきたいです。

弊会には多様な専門性を有する人材が豊富に所属しています。貴社の持続可能な組織づくりを多面的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
i 2025年1月24日朝日新聞デジタルより
https://digital.asahi.com/articles/DA3S16133405.html?pn=2&unlock=1#continuehere
ii LGBT:レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシャル(Bisexual)の3つの性的指向とトランスジェンダー(Transgender)という性自認の各単語の頭文字を組み合わせた表現であり、性的マイノリティの代表的な4つの頭文字をとった総称。他にLGBTs、LGBTQ、LGBTQ+などの表記方法もある
iii 湯浅尚子, “レインボーカフェ2023~中小企業における性的マイノリティ活躍支援事例共有会~,”(一社)東京都中小企業診断士協会令和5年度社会貢献事業活動事例集,pp.46-47,2024年4月
iv 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度「調査・研究事業」 中小企業におけるLGBTQなど性的マイノリティの活躍支援についての調査研究 ~見えづらいダイバーシティとしての性の多様性の理解促進~ https://www.jf-cmca.jp/attach/kenkyu/honbu/r4/lgbtqkatsuyakusien.pdf
v 山口 周. 「世界で最もイノベーティブな組織の作り方 」(光文社新書)
vi https://diversitystudy.tokyo/
vii https://jdio.jp/
viii ファミリー休暇:出産、育児、通院、介護や子供の学校行事、妊活、自己啓発など多様な家族観の社員に広く活用できる制度
ix 日本商工会議所・東京商工会議所「求められる「少数精鋭の成長モデル」への自己変革(これからの労働政策に関する懇談会 中間レポート)」