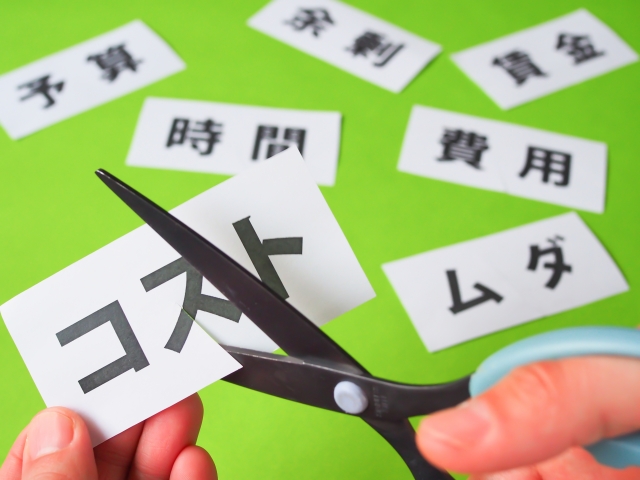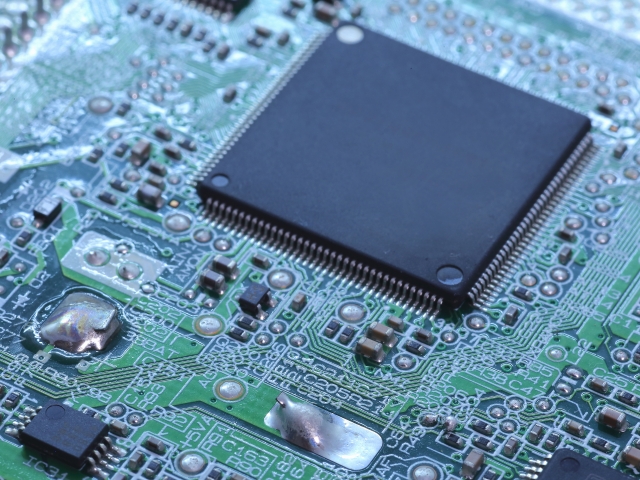過去の記事一覧
-

小規模事業者の方よりご相談の多い、小規模事業者持続化補助金の概要と申請資料「経営計画書兼補助事業計画書①」、及び「補助事業計画書②」の作成方法とポイントについて説明いたします。(齋藤 洋二)
-

課題を解決する最良の方法の1つとして専門家派遣制度を取り上げ、枠組みやメリットなどを紹介する。また、川崎市産業振興財団の専門家派遣制度3種を具体例として紹介し、活用を促進する。(小野 慎介)
-

パワーハラスメントは発生時の対応よりも予防が重要です。防止規定の整備や研修も大切ですが、それよりもハラスメントが発生しづらい職場をつくっていく必要があります。キーワードは「心理的安全性」です。(高橋 美紀)
-

新しい公共サービス「PPP事業」の地産地消傾向が強まっており、PPPの先進自治体である川崎市の事例を提示しながら、川崎の中小企業がビジネスチャンスをつかみ、地域の発展に寄与するように問題提起をします。(望月 信宏)
-

利益の出せる「ものづくり現場」で大切なことは生産性を向上させることですが、そもそも生産性の本質とは何か、そのために現場はどうすればよいのか、原点に立ち返り分りやすく整理したいと思います。(野口 隆)
-

昨年、筆者は法政大学のビジネススクールに在籍し、修士論文「中小企業向け堅牢性向上メソッドFORMの開発」を作成した。本稿では、中小企業が効果的に財務体質を改善する方法として、その要旨を紹介する。(土田 淳)
-

働き方改革関連法の施行により「物流の2024年問題」が懸念されています。この課題に対しては企業による取り組みの他、消費者として草の根の取り組みを行うことができると思います。そうした取り組み「地産地消」を神奈川の消費者の皆さんにお勧めします。(武田 良樹)
-

自己流のプレゼンを「伝わるプレゼン」に!プレゼンテーションの苦手を克服し、ブラッシュアップする、具体的なポイントを紹介します(古山 亮一)
-

業績好調の後に資金不足に陥ることが有ります。変化の激しい事業環境でもしっかり生き残るためには資金管理がとても重要です。そのためには何をどのようにすればよいか、詳しくご説明します。(平田 仁志)
-

厚生労働省の推計では2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると考えられており、その可能性は経営者においても例外ではありません。経営者が認知症になれば、日々の事業継続に限らず多くの問題が予想されます。そこで経営者が認知症を発症した際のリスクと備えについて紹介します。(岩水 宏至)
-

経営課題解決セミナー:明日から使える経営課題解決術を全5回で開催します。未来のために、「新たな挑戦」と「持続可能な経営」を一緒に始めませんか?明日からすぐに使える便利なツールを提供します。
-

DXの重要性の理解は進んでいるものの、実際に取りかかる企業はあまり多くありません。最終的なDXの姿を追い求める前に、第一歩として現場の「見える化」に取り組むことで、成果を出すことができます。(新井 一成)
-

川崎中原工場協会の小林正男会長に工場協会の目指すものや直近の取り組み、特色のある活動について伺いました。(関根 清一)
-

逆境は変化のチャンスであり、経営者にピンチをチャンスに変える発想の柔軟性が求められる。現代の経営環境も変化している。リスクを認識しつつ新たな事業に果敢に挑戦する姿勢が重要だと考えます。(足立 秀夫)
-

厚生労働省の受託事業における女性活躍推進アドバイザーとして、全国津々浦々の中小企業に「真」の女性活躍を目指す組織づくりを支援した筆者が、現場目線で「良かった」事例、「お勧めできない」事例をご紹介します。(宮木 恵美子)
-

これからは脱炭素化・資源循環型経営を成長の機会として捉えていくことが必要です。環境の取組がわからない、社員の協力が得られない等の悩みを抱える一般的な中小企業に対して環境省が策定したEA21の活用の効果をお伝えします。(徳植 義人)
-

現在の社会情勢にあっては納入先に単価の増額をお願いせねばならないケースも多い一方、取引自体を失うことを恐れ踏み出せないケースも多いと思われます。その場合、先ず納入先における自社のポジションを確認してみましょう。(齊藤 拓)
-

2023年5月より新型コロナ感染症が「5類」へ移行になり、アフターコロナのビジネスの動きがでてきました。直近の世界及び日本の政治・経済・社会の動きが、我が国の中小企業へどのような影響を及ぼしいくのかについて考えていきたいと思います。(滝沢 典之)
-

コロナ禍後、国からの様々な施策は知られるようになったが、当会のある川崎市にも補助金や融資制度、事業者のPR等にも活用できる施策は相当ある。本市の施策の内、筆者もよく携わり、事業者にとって活用しやすいものを紹介したい。(島谷 健太郎)
-

「物流の2024年問題」とは、働き方改革関連法によって、2024年4月1日以降、ドライバーの年間の時間外労働時間の上限が、960時間になることによって発生する諸問題に対する総称のことです。今後ドライバー不足、運賃上昇に拍車がかかり、今迄通りの慣習では物が運べなくなる危険性が差し迫っています。物流革新なしには、この危機は乗り越えられません。このように誰もが無関心ではいられない喫緊の物流問題を解説します。(小谷 泰三)
ページ上部へ戻る
Copyright © (一社)川崎中小企業診断士会 All rights reserved.